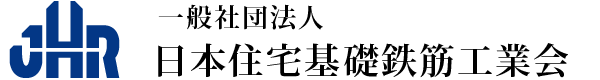住宅用基礎鉄筋ユニットの生産を早くから手がけてきた岡田工業。工業会の設立メンバーでもある。また同社は住宅基礎鉄筋をメインとしながら減震装置、天然石シートの販売、フィリピンでのCADセンター、職人育成事業などを推進。新たな展開を見据える岡田社長に話を聞いた。
JHR会員うちの会社インタビュー 語る人
岡田工業株式会社・代表取締役 岡田健太郎氏

子供たちが大きくなり自分の時間にはゴルフやテニスをするようになった。「テニスは学生時代からで、コロナ前から本格的にやり始め、大会などにもでます」と元気いっぱいだ。45歳。
岡田工業の歴史、現状、工業会へのご意見などお聞きしたいと思います。
岡田 創業は先々代で1963年です。当時はコンクリート二次製品用メッシュの製造がメインでした。創業地は神奈川・川崎なんですが、その後千葉に工場を移し、30年前にこの地に茂原工場を設置して、住宅用基礎鉄筋ユニットVGLベースの製造を始めて現在に至っています。1999年にBタイプの評定も取得しました。
住宅用基礎鉄筋への進出は、当時公共工事が減っていく中で、同じような工場の設備でできるものは何かということで始めました。参入は早かった方だと思います。基礎鉄筋での評定取得は積水ハウス関係の仕事がきっかけだったと聞いてます。
本格的な住宅ニーズとの関わりはその辺からですね。当時住宅が伸びていっていた時代でしたが、基礎の溶接ユニットを使っているところはそれほど多くなかったので、お客さんはどんどん増えていったということです。二階建て用はVGLベースで、その後2006年に工業会の立ち上げの時のメンバーとして加入して、その後BRSの認定も取得しました。
私自身は、芝浦工業大学の大学院を卒業して日産自動車に入りエンジン開発部門に3年間いましたが、その後戻ってこいと言われたわけではないのですが、自から戻ろうかなと考えました。15年前の2009年です。
最初はどんな仕事から始めたのですか。開発ですか。
岡田 うちの会社は開発部門などないので、まず現場の製造ラインに入って溶接、曲げ、切断等を一通りやりました。その後、事務に入っていろいろしました。社員も30人位で今より全然小さかった頃です。工場もここだけで浦安工場も大月工場もありませんでした。得意先も基礎屋さんも結構ありました。
取引形態も、当時は材料支給は少なく、住宅メーカーも工場指定で基礎屋さんはその指定工場から買う形で、我々の取引相手としては基礎屋さんなんです。それがだんだん住宅メーカーがコスト管理や品質管理の観点から、住宅メーカーが取扱う形で基礎鉄筋の取引が増えていきました。そういう意味では、当時の取引先はほとんど基礎屋さんだったような気がしますね。住宅メーカーとの直取引は積水ハウスぐらいだったと思います。
また私が入社した当時は事務処理はすべて手書きでした。受注や配送伝票等の書類は納品日が変わったら横線で消して書いたり、違う紙に書き直すみたいな事をやってました。図面からの材料拾い出しも全部手作業でしたね。
需要が拡大し物量が増えるので対応が非常に大変になり、数え間違いとか様々なミスが出てきてクレーム対応が増加しました。それで、工場だけでなく事務系の仕事も自動化が必要だと思い業務のデータ化、自動化を進めていきました。
入ってみて様々な問題を感じたようですが、基礎鉄筋の業界をどう感じましたか。
岡田 この業界は、プレカットもそうかもしれないですけど、設計は住宅メーカーさん、設計事務所さんがするわけです。こちらは製造工場なので基本的にどういうものを作るのかは、メーカーさんが決める。そのためモノづくり自体には問題がなくても、基礎鉄筋の品質管理とか製造についての考え方等では、いろいろムダなことを随分やってきたと思います。それでムダというか、もっと効率的にできるなと思ったので、会社でそういう部分を変えていくやり甲斐はありましたね。
社長に就任されてから3年になりますが、入社以来の会社の成長の主な理由は何でしょうか。
岡田 今岡田工業としては、工場は120人位、海外が100人位なんで、グループ関連と海外合わせて220人います。入社当時は当時30人位でしたから6、7倍になりました。
会社が成長できた理由は2つあると思います。営業的な面と生産の面です。営業は私と会長が一緒にやってきました。当時は新しいお客さんを増やすこと自体は今ほどは難しくなかったと思います。市場が広がり量も増えていましたしたからね。ただ工場の対応は当時のやり方では大変だった。そのため、システムの開発をしたり、帳票類や加工指示書を自動化しました。そうした改善で顧客増加のスピードに追いついていけた気がします。
また割付けや積算ソフトもなかった時代で、HS+というソフトを私が会社に入ってから直ぐ使い始めました。最初から完全な拾出し積算が出来るわけではなかったのですが、色々なことに活用できるようにしてきました。
今でも手拾いを残している会社の話は聞きますが、うちの社内では手拾いはありません。そのソフトでも100%出来ない部分はありますので、使えるところは使って、使えないところは自社開発の別のソフトを使ってやっています。そのお陰もあって、今ほとんど手拾いはゼロです。
そうした改革や効率化は会社全体の生産性に貢献したましたか。
岡田 事務的にも工場への加工の指示書や請求情報、売上等の情報は全部電子データで作れるようになった。そうすると工場に出す書類も自動で作れるようになりました。売上ソフトは一般的なものを使っていますが、その売上データは積算データを売上データに適した形に変更できるので、見積業務、請求業務が非常に楽になりました。積算が終われば見積書が自動で出てきます。業務軽減に非常に貢献しています。見積・請求業務の担当者数は今も変わっていません。その部分は生産性がかなり上がったと思います。
会社の業務体制や得意先等は今どのようになっていますか。
岡田 今4、5人で請求関係と帳簿類をやっています。当時は積算業務も一緒だったのですが、積算を除けば人数はほぼ変わっていません。出荷量が3倍増えたのでこちらの生産性も3倍近く上がっていると思います。積算の人間は増えました。受付業務、納期調整も含めて積算部門は国内で15人ぐらいです。
工場では製造部で60人いますが、自動加工機の導入で生産性が大きく変わりました。メインの溶接機械はあまり効率化されてなくて変わってない気がします。
一方製品の品質はだいぶ安定的になったと思います。どういうことかというと、役物みたいな細かい部材の切断や曲げなど、溶接以外の工程に自動機械を導入したことによると思います。新しい設備を導入しながら全体的な生産性を上げていったということです。
取引先は、今は住宅メーカーの方が多いですね。顧客の数は住宅メーカー、ビルダー系でいうと20社ぐらいです。地場の工務店さんとは付き合いはゼロではないですが、生産量の六割~七割くらいはハウスメーカー向けです。商圏は東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城一部、遠いところでは高崎ぐらいまで持って行ってます。

お客さんにとって岡田工業の魅力はどんなことだと思いますか。
岡田 以前から製品自体はそれほど変わっていないと思いますが、電子割付をやるようになって、間違いが大幅に減ったと思います。手書きではないので現場で図面が多分見やすくなったということは一つあります。製品自体は変わらないとなると、ソフト面が評価されていると思います。
また会社の魅力という点では難しいかもしれませんが、最近は特に基礎設計の部分に少し突っ込むようにしています。基礎設計自体はしませんが、「こうした方がいいですよ」と相談やアドバイスをするようにしています。そうしたこともこの15年間で仕事が増えてきた要因かもしれません。今、力を入れているところですね。住宅メーカーは上物はよく分かっているのですが基礎についてあまり分からないようですね。当社では鉄筋施工のマニュアルを作って仕様の提案をしています。ソフト面、設計面でサポートができたのかなって思っています。
現場での組立は今はしていませんが、職人不足の今後を考えれば、やらなければならないと再度考えています。今後鉄筋加工だけでは儲からないですから、今後は基礎工事への参入も必要ですね。
来年は基準法が改正されますが、対策を考えられていますか。
岡田 今、個別のお客さん向けに基礎のスパン表を作っています。上物荷重から接地圧を求めて、それに対応する基礎のスパン表をお客さん向けに作るというのをやってますね。住木センターの一般的なものではなく、建物の仕様ごとに配筋量を求めて表にしています。経済設計も意識したスパン表で、建物仕様を一つに固定してしまうと一番重いものに合わせる表になってしまうので、仕様ごとにこの荷重だったらこのスパン表でいけるっていうのを作って提供することを進めています。
今後の新築市場の見通し等をお聞きかせください。
岡田 新築に関わっている基礎鉄筋の市場は小さくなってきますから伸びないでしょうね。特に関東はユニット鉄筋の普及率が結構高いので厳しい。他のエリアは職人減少でユニット鉄筋の使用率が上がっていく部分があると思います。鉄筋業界全体で見れば今後も横ばいか若干下がるんじゃないかと思います。
今、どれくらいの売上規模ですか。生産量や売上規模は。
岡田 売上が37億ぐらいですかね。今年はちょっと下がってますけど、生産量は年間1万8000トン程度です。基礎鉄筋以外の売上は一割ぐらいだと思います。鉄筋以外の部門は、これからですね。今のところ売上が少なくても利益が出ればいいという感じです。海外の部門でアウトソーシング関係の図面部門は、もうちょっと伸びると思いますけど。海外の建材は、まだ伸びしろがあると思います。
会社では日常どんな感じで過ごされていますか。
岡田 自宅が会社の近くにあります。生まれは神奈川なんですけど、小さい頃に千葉に引っ越してきたので、茂原は地元です。始業時間に合わせて出社します。外出しないときは朝8時に来て夜7時ぐらいに退社します。遅いと9時とかぐらいまではいますが、普通は結構早く帰ります。図面の拾出しとかやってた時は12時を超える日もありましたね。今では考えられないですね。今は社員の残業時間も月20時間位が平均です。忙しい時は規定を超えている人もいます。平均年齢は事務所のほうは30代前半ぐらいです。工場を入れても平均40歳ぐらいです。外国人もいますが外国人を入れるともっと若返りますね。
最後に、工業会に対してご意見、ご要望等がありましたらお願いします。
岡田 工業会は情報交換のためだけの場ではないので、今回の四号特例縮小の法改正などに対して、業界的な意義が出てくるのかなと思います。住宅の基礎の鉄筋の仕様はこうあるべきみたいなものを、どんどん打ち出すべきですね。今までは四号特例に隠れて重要視されなかった部分が今後必要になってくると思うので、工業会の存在意義が、今まで以上に重要になると思います。そうなるように世の中にあるべき基礎の情報を発信することが重要だと思います。
■会社プロフィール
本社:神奈川県横浜市中区尾上町4-47
千葉工場:千葉県長生郡長柄町鴇谷1672-1
浦安工場:千葉県浦安市北栄4-15-13
大月工場:山梨県大月市初狩町下初狩431
海外拠点:フィリピン(CAD、積算、実習生研修の各センター、Ishi-Bariショールーム)
年 商:37億円
従業員:120名。